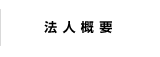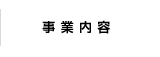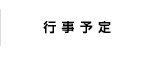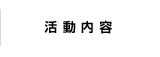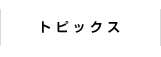第22回文化交流会「都草寄席」 “落語を通して京都のお話を聴く”(2017.9.8)
第22回文化交流会「都草寄席」 “落語を通して京都のお話を聴く”(2017.9.8)
第22回文化交流会は「都草寄席」、題して“落語を通して京都のお話を聴く”。
落語家の桂雀喜さんをお迎えして、9月8日にひとまち交流館の和室で開催されました。
落語の由来、背景に江戸は武家社会、上方は寺社などがあり、高座での室来や道具の違いなど、詳しく説明していただき、生での落語に参加者はひきこまれました。テーブルを2段重ねて高座を作り、毛氈から座布団、見台、ライトに至るまで雀喜さんに持って来ていただきました。
出囃子がうまく操作できなくて、「桂雀喜さんどうぞ」でも音楽が鳴らないので出て来られなかったり、皆様が帰りはじめてからお囃子がなり始めたりしましたが、不手際な所も都草文化交流部手作りの寄席の証でした。
当日は質問にも答えて頂き、雀喜さんの「気負わない事」との助言もありました。
今回は28名の会員にご参加いただきありがとうございました。
お手伝いの方もお疲れ様でした。
(文化交流部 須山里己)



桂雀喜 都草寄席に参加して
9月8日、ひとまち交流館で開かれた桂雀喜さんの落語会に参加しました。
今までのお茶や、和歌などの取り澄ました京文化に代わり、本当の上方の庶民文化である落語に楽しいひと時を過ごしました。
会場は30人ばかりが入るといっぱいの和室に、朱の毛氈の仮設高座が設けられ、雀喜さんと会員が一つになった雰囲気に部屋は盛り上がります。
雀喜さんは大学を出て一旦サラリーマンになりつつも、落語家への道をあきらめきれず、再三桂米朝師匠を訪ね、ようやく桂雀三郎師匠を紹介されて入門を許されました。その他いきさつや弟子としての修行の日々など、日ごろ知られていない舞台裏を語る雀喜さんの姿に一層親しみが感じられました。
落語は清水音羽の滝の茶店を舞台にした「はてなの茶碗」で始まりました。
茶店で憩う京の茶道具屋茶金さんが手にした茶碗を見て「はてな」と首をかしげたことから、油売り商人がそれを名器と見て、なけなしの金をはたき2両で買い取ります。しかし、それがただの水漏れした傷茶碗であったことが分かります。
後日、茶金が首をかしげただけで傷の茶碗に2両の値が付いたというその噂が天子の耳にまで達し、天子が「はてな」と箱書きし、関白の歌まで添えられ、その茶碗が一躍千両になるという夢物語です。
清水寺を落語の題材としたものは、他にも「景清」や「殿集め」などがあります。京の名所を落語の世界から見直すことも楽しい見方です。
最後に雀喜さんと福井大作監事の二人とも得意な中国語を交えてのトークショーもありました。
私の若いころ京都では毎月市民寄席が行われていて、上方落語四天王といわれた今は亡き松鶴、米朝、春団治、文枝等の舞台をなつかしく思い出していました。
(会員 林寛治)



◎桂雀喜さんの経歴
昭和44年5月7日生
平成5年同志社大学文学部卒業
平成5年8月桂雀三郎(桂枝雀二番弟子)に入門
摂津市で桂雀喜の落語会「ジャッキー7」を偶数月に開催、今年2月に100回記念の会を摂津市民ホールで開催
天満天神繁盛亭で春は古典、秋は新作の独演会を開催
(広報部 須田信夫)
(写真 須田信夫)