丹波支部行事 「旧山陰街道に残る丹波の歴史をめぐる」(16.11.27)
都草 丹波支部行事 「旧山陰街道に残る丹波の歴史をめぐる」(16.11.27)
日時:平成27年11月27日(日)雨模様
行程:【馬堀駅集合(9:30)】→馬堀城址➡【篠村八幡宮】→矢塚、旗立楊➡王子神社(闇の宮)➡
めがね橋(田辺朔郎)➡【山陰古道】→三軒屋→船着場→異人道➡子安地蔵(恵心僧都)➡
酒呑童子首塚(首塚大明神)➡山本城址(如意寺)→唐櫃越➡昼食
去る11月27日(日)、生憎のかなり強い雨が降る中を、丹波支部メンバー(5名)プラス熊谷副理事長の参加を得て、首記行事を執り行いました。
篠村八幡宮や酒呑童子首塚などはかなりポピュラーで、いわく因縁や由緒などをご存知の方も多いと思いますが、それ以外の場所は、まさに穴場中の穴場で、歴史好きにはたまらない散策となったと自負しています。私自身も、長年亀岡市に住んでいますが、こんな隠れた史跡がごろごろしているとは全く知りませんでした。 特に普段利用しているJR馬堀駅が、馬堀城址であったとは・・・・。辺りには表示標識は全くなく、城跡を思わせる石垣などもなく、どこが・・・?と思うような場所ですが、周辺の高低差をじっくりと考察してみると、「ブラタモリ」風に、「たしかに!!」と納得してしまいます。
山本城跡も、唐櫃越の入り口に位置しており、明智光秀との因縁も非常に興味深いものです。こうした歴史を知り、当時の武士たちの運命に思いを馳せると、何か切ないものを感じます。

馬堀城址に建つJR馬堀駅

篠村八幡宮、ここで尊氏は北条氏に反旗を翻した

境内の相撲場では
元気な子供たちが稽古に励んでいた

参集した武士たちが矢を立てた矢塚

源氏の白旗がたなびいた楊の木(当時は境内)

篠村八幡宮で井上部長より案内

王子神社(闇の宮)、
鎌倉時代に熊野若一王子を勧奨し正一位の位を受けた。
鬱蒼とした森の中にあったので、くらがりの宮、位有の宮とも云われた

めがね橋(王子橋)、右は国道9号線
田辺朔郎博士が水路閣を作る前にテストで造った橋

山陰古道入口、昔は参勤交代も通ったらしい

三軒屋、往時は旅館や店が立ち並んでいた

船着場跡にて

首塚大明神入口

首塚大明神

酒呑童子の由緒を書いた石碑

からと越(本能寺への道)

山本城跡(からと越え)
今回の行程は、なかなか観光ルートとして、多くの方々が一律に楽しめるというものではないので、一般化するのは難しいと思います。ただ、丹波・亀岡の地理的・軍事的位置づけや、京都との精神的なつながり、人々の思いなどが、こうした史跡などを通して、もう少し認識を広げることができたらなあと考える次第です。
(丹波支部長 井上享一)
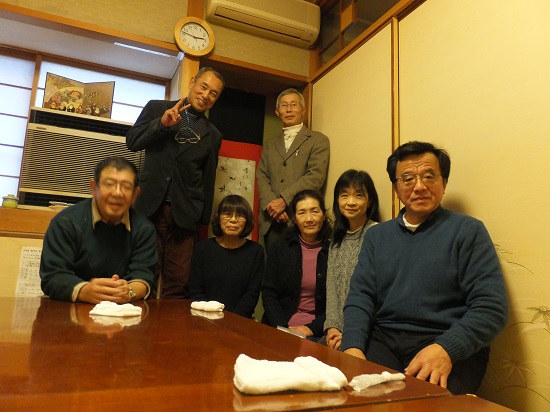
本日の参加者の皆様、お疲れ様でした
(写真撮影:熊谷喜輝)
(広報部:熊谷喜輝)

